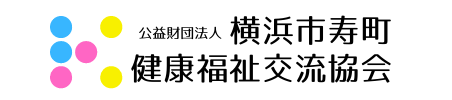まちのあゆみ
寿地区とは
寿地区は、大阪の「あいりん地区」、東京の「山谷地区」とともに、日本三大寄せ場の一つとして数えられています。「寿地区」と呼ばれる地域は、横浜スタジアムから見て、JR根岸線を挟んだ反対側にあり、関内駅から徒歩10分、石川町駅から徒歩5分ほどの位置にあります。
わずか面積0.1km²にも満たない狭い地域ですが、約120軒の簡易宿泊所が密集して建ち並び、6,500人前後の方々が宿泊しています。
埋地七ケ町の誕生
江戸時代の初め、この地域一帯はまだ釣り鐘型をした入り海でした。この頃、江戸幕府により開墾、埋め立て等が盛んに奨励され、開かれた土地はその開墾者、埋め立て者が所有できることになっていました。しかし、入り海で広域な埋め立ては大変難事業で、なかなか手を出す人が現れませんでした。
寛文年間に江戸の大材木商吉田勘兵衛がようやくこの事業を開始しましたが、予想どおりこの埋め立ては難事業で、10年という長い歳月を要しました。将軍徳川家綱は、この新しくできた土地に「吉田新田」と命名し、以後、勘兵衛の子孫である北の吉田家と南の吉田家が代々この土地を支配しました。
しかし、この時の埋め立てでは、現在の寿地区及び周辺にあたる地域一帯に、「南一つ目沼」と呼ばれる湿地帯が残りました。この「南一つ目沼」の埋め立て工事が難事業の末に完成したのは、「吉田新田」誕生から約200年後の明治6年のことでありました。新しくできた土地には、南側から松影、寿、扇、翁、不老、万代、蓬來と7つの町名が付けられ、これを「埋地七ヶ町」と呼んでいます。
戦前の繁栄と戦災
この「埋地七ヶ町」は周辺に運河をめぐらせ運送の便がよいこと、また、日本最大の貿易港として発展してきた横浜港に近いことから、材木店、輸出用の繊維製品、陶磁器の製造そして輸出業者の問屋街として活況を呈しました。
その後、大正8年の大火や同12年の関東大震災で大打撃を受けましたが、太平洋戦争前には、横浜市中央卸売市場分場が寿地区内(今の「横浜市生活自立支援施設はまかぜ」付近)に置かれる(昭和6年)など、物流の一つの中心地として見事な復興を遂げていました。
しかし、昭和20年の横浜大空襲で寿地区一帯は、いくつかのビルを除き全くの焼け野原と化し、終戦後港湾施設とともに米軍に接収されました。
終戦直後の桜木町周辺
寿地区が米軍に接収され戦後の復興から取り残されている間に、大岡川を挟んで隣接する「桜木町」や「野毛地区」は、たくさんの求職者や野宿者であふれていました。これは当時、横浜港が軍用貨物の集積基地や穀物輸入窓口となっていたため、たくさんの荷運び労働者が必要で、「横浜に行けば食べていける」という噂が伝わったために起こった現象でした。
しかし、戦後の就職難・食糧難であえぐ全国から集まった労働者にみあう宿泊施設はなく、野外生活者数が増大し、このため「水上ホテル」と呼ばれる艀の廃棄船を改造した宿泊所も生まれました。
さらに、昭和25年に始まった朝鮮戦争は、軍需輸送の基地として、横浜港の港湾荷役の労働需要を増大させ、以前にもまして全国各地から労働者が仕事を求めて集まってきました。桜木町駅近辺には、野毛の「横浜公共職業安定所」と日雇労働者に仕事を斡旋する「柳橋寄せ場」があり、多数の手配師を通じた青空市場が形成されていました。
寿地区(簡宿街)の形成
昭和31年に寿地区の接収が解除され、それまで野毛にあった柳橋寄せ場と横浜公共職業安定所が寿町に移転すると、寿地区に日雇労働者が集中するようになっていきました。
またこの時期に、水上ホテルが転覆し何人もの犠牲者が出たことや不衛生のために発疹チフスが大流行したことも、新しい場所への移動が緊急に求められ、日雇労働者が寿地区に集まる原因となりました。
そして、この地域の立地条件が、港湾施設に近いこと、地元住民の反対がないこと、職業安定所が移転してきたこと、地価が安いこと等格好の地であったため、日雇労働者を対象とした簡易宿泊所が次々と建設されました。昭和40年頃には、宿泊所の数が80軒余りとなり、現在の寿地区の簡宿街の原型がほぼ完成したといわれています。